僕が絵本専門士になろうと思ったのは、
かつて働いていた図書館で行われた「児童奉仕研修会」のなかで、
おはなし会の読み手としての姿勢、
・「声色は変えない、読み手の感情の起伏はフラットに」とか、
・「季節感を考えて、定番の絵本だって子ども達には、新しい出会いのはず」とか、
おはなし会のメインは、あくまで絵本、「読み手はその媒介者」という棲み分けがあり、
僕としては、そこに違和感を感じていたのです。
もっと、読み手が子ども達に近づいてはいけないのだろうか、
地域の子ども達の成長を見守るのは「絵本」なのか「僕」なのか、と、
最近、地元の図書館で、少しずつ、絵本に関する講座を開催させていただけるようになり、
これまでのトは違う、変化が生まれていることを感じています。
読み手の皆さんが少しずつ、単なる「読み聞かせ」ではなく、
観客と読み手が感情を共有する「ライブ」へとシフトし始めているなと、
おかげさまで、僕の絵本の読み方も少しずつではありますが、
肯定的な評価が増えている用に感じます。
この変化は、絵本の読み方に対する価値観の転換といえるでしょう。
「正しく読む」ことから、「心で読む」ことへ。
絵本は、言葉と絵だけでなく、読み手の感情や空気感によっても語られるようになった。
図書館という公共空間が、静かに本を読む場から、感情を共有する場への転換点に立っているのでは、と感じます。
おはなし会がライブ化することで、絵本はより多くの人にとって「私のもの」に変化していきます。
子どもだけでなく、保護者や地域の人々も巻き込みながら、絵本を通じた共感の輪が広がっていくことは、
少子化社会にあって、子ども達を社会全体で見守っていこうという発想にも合致しているのではないでしょうか、
これからのおはなし会は、ますます「ライブ」としての側面を強めていくのでしょう。(たといいなぁ、)
絵本は、読むものから、感じるものへ。
そして、共に生きるための「対話の場」へと変化していって欲しい、そう願ってやみません。
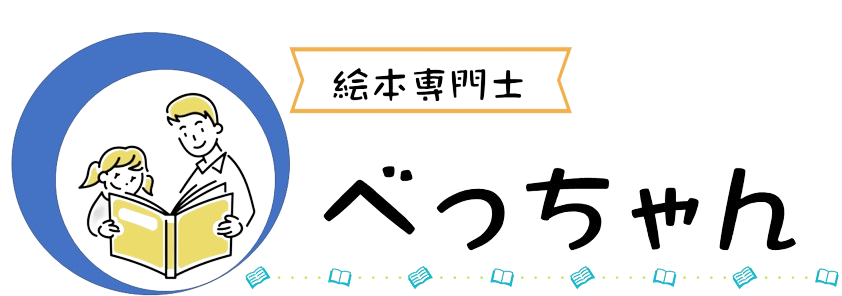
コメントを残す