2月7日付の読売新聞紙上において、読売新聞社と講談社の2社によるて提言、
「書店活性化へ向けた共同提言」が1面記事になっていました。
省庁が連携し策定する予定である「書店活性化プラン」に対する提言であり、
国は、今回の提言を踏まえて同プランの策定を進めるとしています。
提言は5つの分野になされており、
僕が注目したいのは、そのうち、
「書店と図書館の連携を」と
「絵本専門士などを活用し、読書教育の充実を」
の2店について注目しています。
まず、「書店と図書館との連携を」では、
資料費の減少が続く図書館と書店が連携するために
東京都町田市の図書館で予約した本を書店で受け取る事が出来る仕組みや
鳥取県立図書館の地元の書店で資料を購入する取り組みについて事例を挙げており、
地域の中で、図書館と書店が相互に作用する関係性を構築することの大切さを説いています。
特に、ベストセラー作品に関する複本購入の姿勢についての指摘は、
近年の基礎自治体の図書館運営において、
図書館の本来の姿勢を見失い、
市民サービスの名の下に作家の権利を犯している危険性について指摘しており、
行政に携わる末端の一人として耳が痛いです。
また、「絵本専門士などを活用し、読書教育の充実を」についても
本来、公共図書館には、司書という図書館に関する専門職が配置されており、
児童奉仕という分野が確立されているにもかかわらず、
「絵本専門士」という言葉が明記されていることは、
司書でもあり、絵本専門士でもある僕個人としては、少々複雑です。
図書館での読書普及活動が広く社会に影響するに至らなかった、
そう評価されているようにも感じます。
だからといって、絵本専門士が優れていると思っているわけではありません。
ただ、図書館の児童奉仕という分野が今の子ども達、保護者の皆さんの感覚に合致していたのか、
今一度、検証する必要があるのではないか、というのは、僕がこれまでも言い続けてきたことでもあります。
本という文化を安定して、残していくためには、
書店、図書館という垣根を越えて、
誰もが「本を買う」事が当たり前な環境を作らなければいけない、
社会は妄想言うところに来ているのだと言うことについて、改めて考えさせられる提言でした。
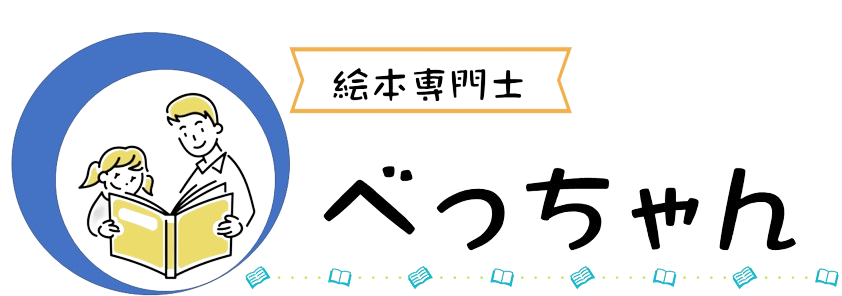
コメントを残す