最近、絵本の歴史に関して少し調べ物をしていてちょっと気付いたことをお話ししたいと思います。
現在の絵本文化の出発点は、
間違いなく、戦後の日本での復興期に重なってくる訳ですが、
不思議なことに、高度経済成長期は、学生運動や市民運動が盛んで、
反戦や民主主義といったテーマが社会の空気を大きく揺らしていたのに、
絵本だけはその“政治の匂い”をほとんどまとわずに、
すっと家庭の中に入り込み、現在まで続いているのです。
特に、反戦・平和というテーマは本来とても大切な価値のはずなのに、
度が過ぎると人を遠ざけてしまうことがある。
主張が強すぎて一般の人から敬遠されることもしばしばです。
でも、戦後最初期の絵本は、同じように「反戦・平和」という願いを持ちながら、
政治的な対立とは無縁のまま、文化として根づいていった。
なぜそんなことが可能だったのか。
僕は、そこに絵本というメディアの特性と、
当時の作家や編集者の姿勢が深く関わっていると思っている。
まず、彼らは「子どもを守る」という強い倫理観を持っていた。
戦前の国家主義教育への反省があったからこそ、
子どもを大人の主張の道具にしないという意識が徹底していた。
だから反戦を語るときも、スローガンではなく、
いのちの大切さや日常の尊さ、他者への思いやりといった普遍的な人間性を描いたのでしょう。
そして、絵本という表現形式そのものが、思想を押しつけることに向いていなかったのではないでしょうか?
絵と文章の組み合わせ、そしてその中から「何か」を感じてもらう事が絵本本来の力ですから、
どんなに強いテーマでも自然とやわらかくなる。
読む人の解釈に委ねられるからこそ、対立を生じにくい構造になっている。
さらに、絵本は家庭という最も非政治的な場所で読まれた。
学生運動が街頭で、政治運動が議会で行われていたのに対して、
絵本は親子の膝の上で読まれた。
家庭の中で語られる反戦の価値は、生活の一部として受け止められたのではないでしょうか。
そして何より、戦後の絵本文化をつくった人たちは、
政治運動家ではなく“文化の人”だった。
松居直、瀬田貞二、石井桃子、かこさとし……
彼らの関心は、子どもに本物を届けること、自由な心を育てること、
文化をつなぐことにあった。だからこそ、
絵本は政治の外側にい続けることができた。
こうして振り返ると、戦後の絵本文化は、
イデオロギーを出発点にしながらも、
子どもと文化を中心に据えたことで、
普遍的な文化として育っていったのだと思う。
これは、絵本というメディアの強さであり、
今も僕たちが絵本に惹かれる理由のひとつなのかもしません。
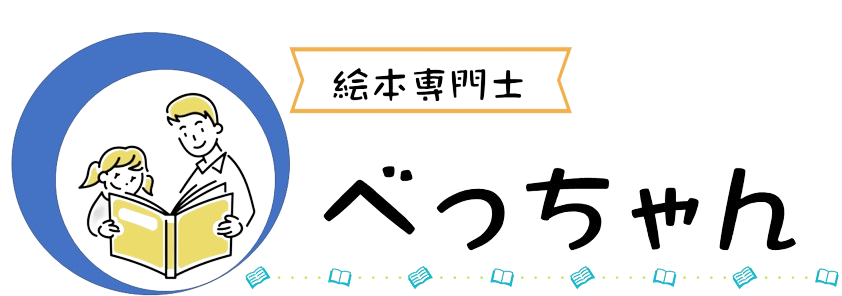
コメントを残す