絵本専門士資格を取っても果たして意味があるのだろうか、というおはなしをなんどかしています。
何しろ、Googleの検索で絵本専門士と検索すると続いてくるのは、
「意味ない」と「落ちた」と「収入」の3つが連想ワードとして出てくるのですから、
資格取得を考えている方や、申込をしたけど受講できなかった方々からの
不安だったり、不満だったりといったものが結構あるんだろうなと思っています。
では何故、意味がないとか収入はどうなっているのか、なんて言うことを検索されちゃうのか、
これはもう、10年も絵本専門士という資格の認定をやっているのに今ひとつ認知度が低く、
活動内容がよくわからないというところにつきると思うのです。
先日、幅広く絵本のされているかたから、
「絵本専門士は何故、おはなし会しかしないのか?」という御質問をいただきました。
僕は、公共図書館等でのおはなし会や、お父さんお母さん向けの講演を中心に活動していますが、
確かに、おはなし会を専業としているように見える、絵本専門士のグループもあります。
では、おはなし会の中で、他の絵本に関係しており、おはなし会を実施している皆さんとの
差別化が出来ているかというと、そうでもないかも、というのが現実かもしれません。
何故だろうと考えてみたのですが、絵本専門士の資格を取る方の中には、
公務員、保育士、図書館司書、出版関係者、メディア関係者、ボランティアを長く続けてきた方、等々、
その出自がバラバラなので、絵本専門士資格を取得した後に、
何を目的にして、どのような活動を行うのかという意思の統一が出来ていないことに問題があるのではないかと、
思い至りました。
結局、絵本専門士資格を取ってもベースが異なるから、意見や活動に相違が生まれる。
違いが生じること自体は悪いことではありませんが、
お客様から見たときに「別に他のおはなし会とかわらないじゃん」
って思われちゃってるかもしれない、という危機感が足りていないのではないかなと、
そんな中なのに、資格を持っていることで、自分が優位に立っていると勘違いする人が生まれてしまい、
その人たちの行動が、「絵本専門士 意味ない」という連想検索に繋がっていく、
これは、悲しいことですが、仕方の無いことだと思います。
資格創設時に有資格者のリスキリングや行動規範というようなものを設定していなかったことが、
今になって、絵本専門士という資格の意義や価値を貶めるリスクになっていると、僕には思えてなりません。
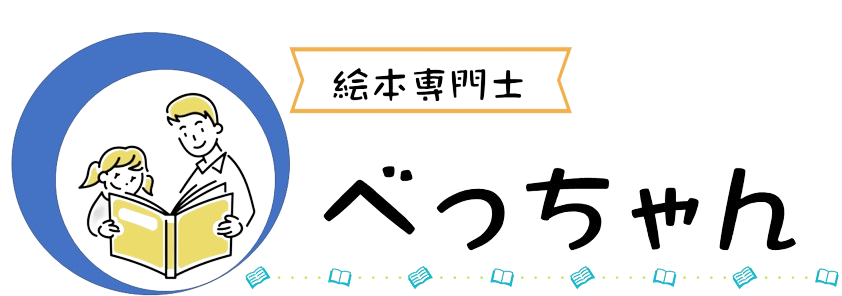
コメントを残す